まぶたが下がる対策とは?原因から効果的なケア・治療法まで徹底解説
- HEIWAMED 0001
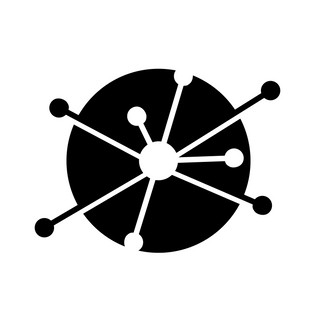
- 2025年10月10日
- 読了時間: 16分
更新日:2025年10月20日
まぶたが下がる(眼瞼下垂)症状は、視界の狭まりや外見上の気になる変化だけでなく、頭痛や肩こりの原因にもなることがあります。本記事では、まぶたが下がる原因や自力での対策法から、手術や注射など最新の治療まで幅広く取り上げます。
多くの方が「加齢だから仕方がない」「遺伝だからどうしようもない」とあきらめがちですが、日常からできる予防策やセルフケアも多く存在します。まずは正しい知識を身につけ、適切なケアや治療法を選択することが大切です。

まぶたが下がる原因(眼瞼下垂)を正しく理解する
まずはまぶたが下がってしまうメカニズムを理解し、原因を明確にすることが大切です。まぶたが下がる症状は、上まぶたの挙筋機能や腱膜のゆるみが主な要因となって起こります。生まれつき自力で瞼を上げる筋力が弱いケースもあれば、加齢に伴う筋力低下や生活習慣の影響を受ける場合もあります。
眼瞼下垂の程度が進むと、視界が狭まるだけではなく、おでこに力が入りやすくなり、頭痛や肩こりなどの全身症状につながることもあります。視機能や見た目の印象が変わるため、本人にとって大きな負担になることがあります。
原因を正しく理解することで、今後のセルフケアや医療的アプローチを選択しやすくなります。まぶたが下がる状態に気づいたら、まずは原因を突き止め、自分に合った対策をとることが重要です。
先天性・後天性・偽眼瞼下垂の違い
まぶたが下がる状態には、大きく分けて先天性と後天性、さらに皮膚のたるみなどによる偽眼瞼下垂が存在します。先天性眼瞼下垂は生まれつき挙筋の力が弱く、幼少期から症状が見られるのが特徴です。
後天性眼瞼下垂は、加齢や生活習慣の影響で腱膜が伸びることで引き起こされます。長期的なコンタクトレンズ使用や目元の酷使が原因になる場合も少なくありません。
偽眼瞼下垂は、まぶたを支える筋肉や腱に問題があるわけではなく、皮膚のたるみによってまぶたが下がって見える状態です。見た目は似ていても原因や治療法が異なるため、正確な診断が重要です。
腱膜性眼瞼下垂やファシアの関係性
まぶたを支える腱膜やファシアが何らかの原因でゆるむと、上まぶたを開く力が低下し、眼瞼下垂が起こりやすくなります。腱膜性眼瞼下垂は特に、加齢による組織の緩みによって顕著にみられるタイプです。
腱膜がまぶたとしっかり繋がっていないことが原因で、皮膚がたるんだり、挙筋の動きが十分に伝わらなくなるケースもあります。ファシアも同様に、筋膜として組織を支えているので、損傷や癒着が起こると機能が低下します。
進行が進むと視界への影響だけでなく、眼精疲労による頭痛や肩こりにつながることもあるため、軽度の症状であっても早めに専門医に相談することが重要です。
加齢によるまぶたの筋力低下とたるみ
年齢を重ねると、筋力や皮膚の弾力は徐々に低下します。まぶたの周りの皮膚は特に薄くデリケートなため、加齢の影響でたるみが顕著に現れがちです。このような加齢変化によって挙筋そのものの活動も弱まり、まぶたが下がりやすくなることがあります。さらに、瞼板と腱膜の結合部が弱くなると、まぶたを開けるために必要な力が伝わらなくなります。
結果として「眠そうに見える」「視界が狭い」といった外見上の変化だけでなく、慢性的な肩こりや首のコリなどの症状が出る可能性があるため注意が必要です。
メージュ(Meige)症候群なども要注意
まぶたがけいれんする眼瞼痙攣や、まぶたばかりでなく口の周囲の痙攣症状を伴うメージュ症候群など、神経系の疾患が原因でまぶたが下がるケースも存在します。神経系のトラブルにより、上まぶたの正常な動きが妨げられるのです。
特にけいれんが続く場合や、目元の違和感が長期間にわたって続くような場合には、神経内科や眼科を受診して検査を受けることが大切です。
これらの病気が見落とされると、適切な治療が遅れ、眼瞼だけでなく全身の健康にも影響を及ぼす可能性があります。
まぶたが下がる症状と進行度のチェックポイント
まぶたの下がり具合による自覚症状や、日常での見落としがちなポイントを確認します。
まぶたが垂れ下がりはじめると、最初のうちは自覚しにくいことも多いものです。しかし、視界の端が見えづらくなったり、顔全体が疲れた印象になるなど、いくつかのサインがあります。
特に、意識せずおでこを持ち上げて視界を確保している場合や、頭や首を反らす姿勢が多くなったと感じるなら進行度が高いかもしれません。
自身の目元の症状を早期にチェックしておくことで、適切なケアや治療のタイミングを逃さずに済むでしょう。
視界の狭まり・額への負担といった自覚症状
まぶたが下がると、視界が自然に狭まります。そのため額に余計な力を入れて視界を確保しようとするため、額や眉間にしわが寄りやすくなり、頭痛や肩こりの原因になることもあります。
長期間、その状態を放置すると首周りや背中の筋肉までこわばり、全身的な問題につながるケースも見受けられます。普段からまゆの上げ下げに疲れを感じるようになったら、一度鏡で自分のまぶたをチェックするとよいでしょう。
些細に思える違和感でも、早い段階で気づくことで症状が深刻化する前に対策を取ることができます。
重症度分類とセルフチェック方法
まぶたの垂れ下がりを数段階に分類し、まばたきや下向き視線での動きなどを診断の基準にすることがあります。例えば、まぶたが瞳孔の上部にかかる程度か、それとも瞳孔部分を覆い始めているかなどで分類されます。
簡易的なセルフチェックとして、片目ずつまぶたを上に引き上げる力や、視界にどの程度さえぎりがあるかを観察する方法があります。加えて顔全体の写真を撮っておき、数カ月単位で変化を比較する方法も有効です。
もし重度の段階に進行していると感じられる場合は、早めに眼科や形成外科など専門医に相談し、適切な治療やケアを受けることを検討しましょう。
まぶたが下がるリスクファクターや生活習慣
普段の何気ない習慣がまぶたに負担をかけている可能性があります。
眼瞼下垂は、遺伝や加齢だけが原因ではありません。生活習慣や仕事環境から生じるストレスがまぶたに影響を与えることも多々あります。
例えば、コンタクトレンズの装用が長年にわたるケースでは腱膜に繰り返し負荷がかかっている可能性があります。また、紫外線を浴び続ける環境やスマートフォンの画面を長時間見続けることも、目元の負担を大きくします。
日常的にまぶたに負担をかける要因を知り、できる限り軽減するような工夫をすることが、将来的な眼瞼下垂のリスク低減につながります。
コンタクトレンズやアイプチが及ぼす負担
ハードコンタクトレンズを長期間使用すると、まぶたを頻繁に引っ張り上げる動作が習慣化され、腱膜が伸びやすくなります。また、アイプチやアイテープもまぶたへの負担が大きく、眼瞼下垂の引き金となることがあります。
これらの負担を減らすには、コンタクトレンズの使用時間を短くしたり、眼鏡との併用を検討するなどの対策が効果的です。メイクの際にアイプチなどを使用する場合も、方法を見直したり、まぶたに優しい製品を選ぶことが欠かせません。
特にまぶたの薄い日本人は、腱膜が傷つきやすい傾向があります。ほんの少しの無理な動作でも負担をため込まないよう、日頃の使用方法を見直すようにしましょう。
長時間のVDT作業や紫外線ダメージ
パソコンやスマートフォンなどを凝視する時間が長いと、まばたきの回数が減り、目元周辺の筋肉に大きな負担がかかります。これにより疲れ目が進行し、まぶたを持ち上げる筋肉にも悪影響を与えやすくなります。
また、日差しが強い屋外に長時間いると、紫外線による皮膚の弾力低下が生じます。まぶたは皮膚が薄いため、シワやたるみに加速がつきやすい部位です。
日常的にUVカットのサングラスや日焼け止めを活用し、さらに休憩時間をこまめに設けるなど、できる範囲で目元を休ませる習慣づくりが肝心です。
遺伝的要因・職業的リスク
家族の中に眼瞼下垂の症状を持つ人がいると、遺伝的に同じ症状を発症しやすいことがあります。ただし、家族性症例であっても早期のケアや手術によって進行を食い止めることは可能です。
また、長時間近くを見る作業を強いられる職場環境や、まぶたを常に酷使する仕事(顕微鏡の使用など)にもリスクが潜んでいます。職業的な縛りがある場合でも、定期的に休憩を入れたり、セルフケアを徹底したりすることで対処できます。
生活や仕事のスタイルを見直してみると、意外とまぶたに負担をかける場面が多いことに気づくかもしれません。気づいた時点で対策を開始し、リスクを最小限に抑えましょう。

セルフケアと日常生活でできる予防策
自宅で簡単に取り入れられるケア方法や生活習慣の改善でリスクを下げることが可能です。
まぶたが下がる症状は、セルフケアによって緩和・進行を抑えることができます。正しく行えば、手術や専門的治療を先延ばしできる可能性もあります。
ただし、自己流のケアはかえってまぶたを傷めるリスクもあるため、やりすぎや誤った方法には注意が必要です。まぶたは皮膚が薄い上に、デリケートな神経・血管が分布しているため、優しくケアすることが大切です。
以下のようなケアや習慣を実践して、まぶたへの負担軽減を心がけましょう。
マッサージは逆効果?正しいまぶたのケアを知る
まぶたの周辺は非常にデリケートなため、強い刺激を与えるマッサージは逆効果になることがあります。皮膚をこすったり引っ張ったりすると、腱膜や筋肉に無理な負担を与え、かえってたるみを進行させる可能性があります。
正しいマッサージとしては、血行を促進する程度の軽いタッチを意識し、目元専用のクリームやオイルを使用するとよいでしょう。ゴシゴシとこするのではなく、温めた指先で優しく押さえる程度を心がけます。
もし腫れぼったさや疲れが気になる場合は、冷温を交互に当てるなどのケアも取り入れつつ、基本的には優しいタッチを遵守するようにしましょう。
眼瞼挙筋トレーニング・ストレッチの方法
まぶたを引き上げる筋肉を鍛えるトレーニングとしては、ゆっくりまぶたを閉じたあとに少しだけ力を入れて開く動作を繰り返す方法があります。これにより、上まぶたの挙筋に適度な負荷をかけることができます。
また、額の筋肉に頼りすぎないよう、鏡を見ながらまぶた単体で上下動をコントロールする練習をするのも有効です。深呼吸をしながら行い、急激に引っ張り上げないことがポイントとなります。
このようなストレッチやトレーニングは、やりすぎや過度な力の入れ方に注意しましょう。適度に行えば、まぶたの筋肉を維持しやすくなります。
スキンケアや紫外線対策でたるみを防ぐ
皮膚の老化を防ぐためには、日常的なスキンケアと紫外線対策が欠かせません。まぶたの周りには専用の保湿クリームを使うなど、敏感な部位に合った製品を選ぶことが大切です。
紫外線はまぶた周辺のコラーゲンを破壊し、たるみやシワの原因を作りやすいです。外出時には帽子や日傘を使いつつ、UVカットの化粧品を活用するなど、対策を徹底しましょう。
毎日のケアが習慣化されると、まぶたの弾力や肌のハリを維持しやすくなります。年齢を重ねても、極力たるみの少ない目元を保つために早めの取り組みが効果的です。
疲れ目対策と目元をいたわる習慣づくり
パソコン作業やスマホの使用時間が長い人は、一定時間ごとに目を閉じる、遠くを眺めるなどの休息を入れる習慣を付けましょう。まばたきの回数が減ると目が乾き、まぶたの筋肉も疲れが蓄積しがちです。
また、温かいタオルを目の上に乗せて血行を良くしたり、就寝前に目元用パックを取り入れるのも有効な方法です。特に目が疲れた状態を放置すると、まぶたを上げる筋肉にも影響が及びます。
習慣的に小まめな休憩を取り、目やまぶた周辺をいたわることで、眼瞼下垂のリスクを和らげるだけでなく、視力維持や疲労軽減にもつながります。
医療的アプローチ:手術・注射・その他の治療
重度の場合やセルフケアで改善しにくい場合には、専門医による医療的アプローチが必要です。
まぶたが大きく下がり始め、日常生活に支障をきたしていると感じる場合には、医療的なアプローチが検討されます。症状の原因や重症度によって、手術や注射など多様な治療があります。
どの治療が適切かは、個々の眼瞼下垂のタイプや健康状態によって異なります。最近ではメスを使わない治療法も登場しており、ダウンタイムが短い施術を希望する人が増えています。
以下では代表的な手術方法や注射治療、および術後のアフターケアなど、それぞれの特徴を解説します。
挙筋前転術・挙筋短縮術
まぶたを引き上げる筋肉(眼瞼挙筋)を短く調整する手術が、挙筋短縮術です。これにより、腱膜が持つまぶたの引き上げ力を高め、眼瞼下垂を改善する狙いがあります。
挙筋前転術は、眼瞼挙筋を前方に移動させることで、より大きな引き上げ力を得る方法です。どちらも比較的ポピュラーな手術であり、重度の症例にも対応できるメリットがあります。
ただし、術後は腫れや内出血が一定期間続くことがあるため、ダウンタイムについて理解し、適切なケアを行う必要があります。
重瞼部・眉毛下皮膚切除術
皮膚のたるみが原因で偽眼瞼下垂を起こしている場合は、重瞼部(上まぶたの折り目)や眉毛下の余分な皮膚を切除し、たるみを取る手術が選択肢となります。
この手術により視界が広がり、同時に二重幅などの調整も可能な場合があります。美容外科・形成外科の領域でもよく行われる手術です。
一方で、切開を伴うため傷跡が残るリスクがあります。腫れや内出血など術後の経過も個人差がありますので、専門医と十分に相談してから進めることが肝要です。
筋膜吊り上げ術
骨格や筋肉の状態によっては、前頭筋に筋膜を吊り上げてまぶたを引き上げる方法が採用されることがあります。これは筋力がかなり落ちている先天性眼瞼下垂に対応するための術式です。
人工素材から自身の大腿筋膜や側頭筋膜を利用する場合まであり、術式によってダウンタイムや仕上がりが異なります。特に他の術式では十分にまぶたが上がらない場合に検討されることが多いです。
患者の希望や全身状態によって術式を選ぶため、選択の際にはリスクやメリットをしっかり理解しておきましょう。
ミュラー筋タッキング
上まぶたを引き上げる役割を担うミュラー筋を短くして、まぶた全体を上げる手術法です。結膜側からアプローチする場合が多いため、皮膚表面の傷跡が目立ちにくいメリットがあります。
ただし、適応症例が限定的であり、腱膜性眼瞼下垂の方には向いていない場合もあります。眼科専門医との十分なカウンセリングが必要です。
比較的軽度の眼瞼下垂や、周囲組織に大きなダメージがない症例で行われることが多く、入院を必要としない日帰り手術として扱われることもあります。
ただしミュラー筋と眼瞼痙攣の関連性が注目されているため、当科では行なっていません。
メスを使わない治療法の可能性
近年では、メスを使用せずにレーザーやラジオ波でまぶた周辺の皮膚を引き締める方法が登場しています。傷を残したくない、ダウンタイムを短くしたいという方に注目されています。
しかし、症状の進行度によっては効果が限定的であり、皮膚や筋肉のたるみが顕著な場合には回数を重ねても十分な改善が得られないことがあります。
手軽さと効果の両面から検討し、場合によっては手術との併用も選択肢に含めることが望ましいでしょう。
術後のアフターケアと再発防止のポイント
手術後は腫れや内出血が引くまでに数日から数週間かかります。医師の指示に従い、術後の通院や洗顔・メイクの制限に注意することが大切です。
腫れが落ち着いてからも、まぶたに負担をかけすぎない生活習慣が再発防止には不可欠です。コンタクトレンズの長時間使用や無理なマッサージは再発リスクを高めます。
また、定期的に目元の状態を自身でチェックし、万が一の変化があれば早めにクリニックを受診することが、長期的な効果を維持するコツとなります。
腱膜修復やファシアリリース法とは?
腱膜がダメージを受けていたり、癒着が原因で可動域が狭くなっている場合に、腱膜修復手術やファシアリリース法が選択肢になることがあります。これは、まぶたを正しく上げるための組織を修復・再生する手術です。
ファシアリリースは、硬くなった筋膜をほぐして柔軟性を回復させる施術で、他の外科的治療と組み合わせることも多いです。
根本的に組織を整えることでまぶたの下がりを改善し、再発率を抑えていくアプローチといえます。
注射療法(ボツリヌス注射)の効果と注意点
眼瞼けいれんや特定の神経性疾患が原因でまぶたが下がる場合、ボツリヌス注射を使ってけいれんを抑える治療を行うことがあります。
ただし、ボツリヌス注射は筋肉の動きを弱める作用であり、根本的な眼瞼下垂の原因改善とは異なるため、あくまでも補助的な位置付けです。
効果の持続期間は数カ月程度で、定期的な再注射が必要となるケースもあり、副作用やアレルギーリスクについては必ず医師の説明を受ける必要があります。
まぶたが下がる(眼瞼下垂)と関連する主な疾患
まぶたが下がるのは単独の症状だけでなく、全身や神経系の疾患と関連する場合があります。
眼瞼下垂は、単に加齢や生活習慣だけで起こるわけではありません。神経系や全身疾患が背景に存在するケースもあり、その場合は根本原因の治療が第一となります。
主に眼瞼痙攣やメージュ症候群などの神経疾患が挙げられますが、甲状腺疾患や重症筋無力症、脳動脈瘤、ホルネル症候群といった病気との関連も指摘されています。
メージュ(Meige)症候群などの神経疾患
メージュ症候群は、顔面やまぶた、口元のけいれんを主症状とする神経疾患です。目の周りの筋肉が痙攣を起こすため、まぶたを正常に開けづらくなったり、意図せず閉じてしまうことがあります。
こうした神経疾患は専門的な検査や神経内科の診察が必要です。まぶたが下がる症状の裏に、思わぬ神経系のトラブルが隠れているケースもあるので要注意です。
治療にはボツリヌス注射が使われることが多く、症状を一時的に緩和する効果が見込まれます。
その他の全身疾患との関係
甲状腺や副甲状腺などホルモンバランスに関わる臓器の不調がまぶたの筋力低下を招くこともあります。まぶたが下がるだけでなく、体重の異常増減や疲れやすさなど全身症状を伴う場合は、内科的検査も検討する必要があります。
重症筋無力症は、まぶたを開ける筋肉の神経伝達がスムーズにいかなくなる病気です。夕方になると症状が強くなる特徴があり、重度の眼瞼下垂を引き起こす可能性があります。
いずれの疾患も早期発見と適切な治療が大切です。まぶた以外にも気になる症状がある場合は、複数の診療科で包括的に検査を受けると良いでしょう。
まとめ・総括
まぶたが下がる症状への理解と正しいケア・治療の選択が、快適な視界と健康維持につながります。
まぶたが垂れて閉じにくくなる眼瞼下垂は、見た目だけでなく視界の確保にも支障をきたす症状です。
先天性から加齢や生活習慣、神経疾患など、さまざまな原因が存在します。
予防や軽度のケアとしては、目をこすらない、コンタクトレンズやアイプチの使用時間を短くする、適度な休憩やスキンケアを取り入れるなどが挙げられます。これらの努力で進行を抑えつつ、必要に応じて専門医と相談して適切な治療を受けることが重要です。
日常のちょっとしたケアや生活習慣の見直しが、将来の眼瞼下垂リスクを下げることにつながります。重症化する前に早めに対策を取り、明るく健康的な目元を保ちましょう。


