瞼が下がる原因・症状・治療法を徹底解説
- HEIWAMED 0001
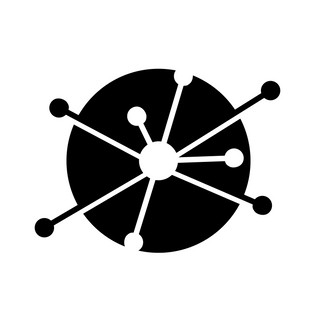
- 2025年10月13日
- 読了時間: 7分
更新日:2025年10月20日
まぶたが下がる(眼瞼下垂)症状は、加齢や生活習慣、神経や筋肉の異常など複数の要因によって起こります。放置すると視界の狭まりや肩こり、頭痛など日常生活への影響も大きいため、原因や治療法を正しく理解しておくことが大切です。
瞼は思った以上に目の機能や見た目に大きく関わっており、わずかな下垂であっても疲れ目や肩こりを引き起こすことがあります。特に、生活の質を維持するためには注意深い観察や早期の対策が欠かせません。
この記事では、まぶたが下がる原因や種類、それによって生じる症状から手術を含めた治療法の概要まで、分かりやすく解説していきます。正しい情報を得て、必要に応じたケアや受診を検討してみてください。

瞼が下がる(眼瞼下垂)とは?まず知っておきたい基礎知識
まず、瞼が下がる(眼瞼下垂)症状とその基礎知識について確認しましょう。
瞼が下がる状態を総称して眼瞼下垂と呼び、上まぶたを引き上げる筋肉や腱、または神経の問題によって発生します。一般的に見た目からも分かりやすい症状ですが、若いうちは軽度の下垂を見過ごしてしまいがちです。症状が進むと視界が制限され、無意識に眉毛や額の筋肉を使って目を開こうとするため、肩こりや頭痛につながりやすいので注意が必要です。
瞼が下がる主な原因
まぶたが下がる主な原因として、筋肉や腱、神経、加齢など多様な要素が関わってきます。
眼瞼下垂というと、生まれつきの先天性のものだけに注目されがちですが、実際には加齢による筋肉の弱化やコンタクトレンズの長期使用、外傷などさまざまな要因が関連します。とくに大人になってから下垂が進む後天性眼瞼下垂では、挙筋腱のゆるみが大きな要因となることが多いです。さらに、さまざまな神経や筋肉の病気によってもまぶたを上げる機能が低下するため、自己判断せずに専門医の診察を受けることが望ましいでしょう。
眼瞼下垂のメカニズムと種類
眼瞼下垂は、瞼を上げる挙筋やミュラー筋といった筋肉の機能低下や腱のゆるみによって起こります。先天性の眼瞼下垂は、遺伝的に筋肉の発達が不十分な場合や、まぶたを上げる腱が弱い場合が原因で、生まれつきまぶたが上がりにくい状態にあります。後天性の眼瞼下垂では、加齢やコンタクトレンズの装用習慣などが筋肉への負担を大きくするため、症状が進行しやすいのも特徴です。
偽眼瞼下垂とまぶたのたるみ
偽眼瞼下垂とは、加齢による皮膚の弛緩や脂肪の偏りなどでまぶた全体が下がっているように見える状態を指します。挙筋や腱そのものの機能は保たれているため、本質的には眼瞼下垂とは異なりますが、見た目としては似たような印象を受けることが多いです。軽度のたるみの場合は、セルフケアである程度改善が期待できますが、重度になれば手術で皮膚の余剰分を取り除く方法が検討されます。
神経や筋肉の異常:動眼神経麻痺や重症筋無力症など
動眼神経麻痺や重症筋無力症などの神経・筋肉の病気が原因で、まぶたを上げる力が著しく弱まる場合もあります。例えば動眼神経麻痺では、まぶたを含む眼球運動に関わる神経が障害されるため、片側性または両側性に瞼が下がることがあります。発症が急性の場合、脳血管障害など重篤な原因が潜んでいる可能性も否定できないため、早急な医療機関の受診が大切です。
加齢・コンタクトレンズ・外傷など生活習慣や環境要因
後天性眼瞼下垂では、加齢による筋肉や腱の弱化が最も多い原因として挙げられます。さらに、コンタクトレンズを長期にわたって使用することでまぶたに過度な引っ張りや摩擦が生じ、挙筋腱にダメージが蓄積されることも珍しくありません。外傷によってまぶた周囲の組織が損傷した場合も、眼瞼下垂の引き金になる場合があります。
片目だけ瞼が下がる場合・急に下がった場合の注意点
特に急激な発症や片側だけの症状には、早めに医療機関を受診する必要があります。
まぶたの下垂が片目のみに見られる場合、加齢などの一般的な要因よりも、局所的な神経障害や筋肉の異常が関係している可能性があります。急に症状が出たときは、脳梗塞などの深刻な疾患の兆候とも関連するため、自分で対処せず専門医に相談しましょう。時間をおかずに受診することで、重篤な病気の早期発見や重症化の防止につながるケースがあります。
脳梗塞・脳動脈瘤など重篤な疾患の可能性
脳梗塞や脳動脈瘤の発症が原因で、動眼神経が圧迫もしくは損傷を受けると、片側のまぶたが急激に下がるケースがあります。頭痛や目の奥の痛み、視界の異常などを伴う場合は特に注意が必要です。いつもと違う強い症状が出るならば、ただちに医療機関を受診しましょう。
糖尿病や筋肉疾患によるリスク
糖尿病性末梢神経障害が起きると、眼瞼を上げる筋肉に指令を送る神経伝達がうまく働かなくなり、まぶたの下垂が生じる場合があります。重症筋無力症などの筋疾患でも同様に、まぶたを持ち上げる力が不足しやすくなります。これらの疾患が疑われるときは、血液検査や神経・筋の検査を含む総合的な診断を受けることが重要です。
瞼が下がることで起こる症状と日常生活への影響
視界の狭まりによる疲労感や肩こり、外見上の印象など、まぶたの下垂が日常生活に及ぼす影響は少なくありません。
まぶたが下がると、物理的に視野が遮られるだけでなく、無意識に目を大きく開けようとするため顔や首に余計な力が入るようになります。その結果、肩や首筋のコリ、頭痛、さらには集中力の低下が起きやすくなります。外見的にも眠たそうな印象を与えがちで、人と接するときの第一印象に影響を及ぼす場合があります。長期にわたり放置すると、慢性的な疲労感や猫背など体全体のバランスを崩す要因となるため、早めの対処が望まれます。
自力でできる対策:セルフマッサージやテープの活用
根本的な治療には医療行為が必要な場合が多いものの、日常的なケアで症状を軽減できることもあります。
軽度の下垂であれば、まぶた周辺の血行を促す軽いマッサージやホットアイマスクなどで疲労を緩和する方法が試みられます。まぶた用のテープを貼って視界を広く保つ応急処置は、日中の作業効率を維持するうえで役立ちますが、長期的な改善を見込むのは難しいです。根本的に原因を取り除きたい場合は、専門医の診察を受けて、適切な治療法を検討することをおすすめします。
外科的治療と保険適用:手術の方法と費用の目安
まぶたのたるみが日常生活の質を大きく下げている場合は、外科的治療が選択肢に入ります。保険適用の有無や費用の目安を把握しておきましょう。
一般的な手術法には、挙筋の腱を短縮してまぶたを引き上げる挙筋前転法や、前頭筋を使った吊り上げ術などがあります。保険適用となるのは機能的な障害が認められる場合が多く、実際に視界が狭くなるなど日常生活に支障が出ているかどうかが判断材料となります。手術の費用は症状や施設によって異なりますが、保険適用時は比較的負担が軽減されやすく、10万円未満から20万円半ば程度を目安に考えておくとよいでしょう。
医療機関を受診するタイミングと診察の流れ
まぶたの症状が続く、急に悪化するなどの場合には早期の受診が大切です。受診の流れと診察のポイントを確認しましょう。
まずは眼科や形成外科を受診し、視野検査や眼瞼機能の評価を行うことが一般的です。必要に応じて神経や筋肉の検査を追加で行うこともあり、検査結果に基づいて治療方針が決定されます。治療を検討する際は、将来の見え方や見た目への影響などを含め、医師と十分に相談することが重要です。
まとめ:瞼が下がる症状に悩む前に知っておくべきこと
まぶたが下がる原因や症状、治療法について理解を深め、適切な対処を目指しましょう。
瞼が下がる症状は、多岐にわたる原因によって引き起こされ、加齢や神経筋疾患、生活習慣などの影響を受けます。早めに正しい知識を得て医療機関を受診すれば、視界の改善や肩こりの軽減など、日常生活の質を高める効果が期待できます。セルフケアによる軽減策もありますが、根本的な改善を求める場合は手術などの専門的な治療を検討することが大切です。自分の症状やライフスタイルに合った対策を見つけ、無理のない範囲でアプローチを行いましょう。


